『呪術廻戦』のギャグは、時に「寒い」と感じることがあります。
しかし、これらのギャグには単なる笑いを超えた、キャラクターの性格や作品の世界観を表現する役割が隠されていることも。
本記事では、呪術廻戦のギャグが「寒い」と言われる理由を考察し、違う視点から楽しむ方法について解説します。
- 呪術廻戦のギャグが「寒い」と言われる理由
- 代表的なギャグとその意図を考察
- ギャグを違う視点から楽しむ方法
呪術廻戦のギャグはなぜ「寒い」と言われるのか?
『呪術廻戦』のギャグは、読者によって「面白い」と感じる人と「寒い」と感じる人に分かれることがあります。
では、なぜ呪術廻戦のギャグは「寒い」と言われるのでしょうか?
本章では、その理由を考察し、ギャグの意図について深掘りしていきます。
ギャグに昭和テイストが含まれている
呪術廻戦のギャグは、昭和や平成初期のネタを含んでいることが多いのが特徴です。
例えば、五条悟の発言や虎杖のノリには、昭和のバラエティ番組を思わせる要素が散りばめられています。
- 五条悟の「飯食べ行こうか」というセリフ → 昭和のコント風の言い回し
- 虎杖のギャグ → 昔の芸人のネタを引用することが多い
- 釘崎のツッコミ → 古典的な漫才スタイル
このようなレトロな要素が、現代の若い読者には馴染みがなく、「寒い」と感じる要因となっている可能性があります。
キャラクターの性格を表現するための演出
呪術廻戦のギャグは、単なる笑いを取るためではなく、キャラクターの個性を際立たせる役割も果たしています。
特に、虎杖悠仁や五条悟は、周囲の緊張を和らげる役割として、頻繁にギャグを挟んでいます。
- 虎杖悠仁:重い展開の中でも、明るく振る舞うことで場の空気を変える
- 五条悟:圧倒的な実力を持つが、軽いノリを維持することで周囲との距離を縮める
このように、ギャグはキャラクターの深みを出すための演出でもあり、一見「寒い」と思えるギャグにも、物語の流れを調整する役割があると考えられます。
次章では、作中の代表的なギャグをピックアップし、その意味を考察していきます。
代表的な「寒い」と言われるギャグ
呪術廻戦には多くのギャグシーンが登場しますが、その中でも特に「寒い」と言われることが多いギャグがいくつかあります。
しかし、これらのギャグにはそれぞれの意味や背景が隠されていることも。
本章では、代表的なギャグをピックアップし、その意図を考察します。
虎杖の「おっぱっぴー」の意味
虎杖悠仁が作中で突然「おっぱっぴー」と言い出すシーンがあります。
これは2007年頃に流行した芸人・小島よしおのギャグであり、現在の若い世代には馴染みが薄いため、「寒い」と感じる人もいます。
- 昭和・平成初期のネタを虎杖が使うことで「ズレた感覚」が演出されている
- 呪術廻戦のシリアスな展開とのギャップを生み出している
このように、あえて古いギャグを取り入れることで、虎杖の無邪気さや周囲との温度差を際立たせているとも考えられます。
五条悟の独特なボケ
五条悟は作中で数々の独特なボケやふざけた言動を見せます。
特に「無量空処」を発動する直前に、急にふざけたセリフを入れることで、相手との温度差を作り出すことがよくあります。
- 例:「無量空処…ドーン!」
- 敵との戦闘中でも油断したような態度をとる
これは、五条が圧倒的な実力を持ち、相手を全く恐れていないことを示すための演出だと考えられます。
そのため、単なる「寒いギャグ」ではなく、彼の余裕や性格を強調する役割を持っているのです。
虎杖&釘崎の東京観光ネタ
虎杖悠仁と釘崎野薔薇が、京都姉妹校交流会の前に東京観光を楽しむシーンがあります。
しかし、この観光中の会話や行動が「寒い」と感じる人もいるようです。
- 二人のやり取りがコントのようなテンポになっている
- 観光中でも真剣な会話がほとんどない
しかし、このシーンは呪術師として戦う日常から少し離れ、彼らの人間らしい一面を見せるための重要な場面でもあります。
このように、呪術廻戦のギャグには、物語の流れを和らげたり、キャラクターの個性を引き出す役割があることがわかります。
次章では、「寒い」と言われるギャグを違った視点で楽しむ方法について解説します。
違う視点からギャグを楽しむ方法
呪術廻戦のギャグは「寒い」と感じることがある一方で、物語の重要な要素として機能しています。
ギャグの背後にある意図を理解すると、作品の魅力をより深く楽しめるかもしれません。
本章では、呪術廻戦のギャグを違う視点から楽しむ方法を解説します。
ギャグの背後にある意図を理解する
作中のギャグは、単に笑いを取るためだけでなく、キャラクターの性格や関係性を強調するために使われています。
例えば、虎杖悠仁や五条悟のふざけた言動は、戦闘やシリアスな展開とのコントラストを生み出し、読者にメリハリを感じさせる効果があります。
- 五条悟のギャグ → 圧倒的な強さを象徴する「余裕の表現」
- 虎杖悠仁のギャグ → 彼の「明るく人懐っこい性格」を表す
- 釘崎野薔薇のツッコミ → 「合理的な性格」との対比を演出
このように、ギャグにはキャラの魅力を引き出す仕掛けが含まれているため、表面的な「面白い・面白くない」だけで判断するのはもったいないのです。
作品全体の世界観を踏まえて考える
呪術廻戦の世界は、呪霊との戦いや術師同士の対立など、非常にシリアスなテーマを描いています。
そのため、キャラが場を和ませるためにギャグを挟むのは、物語全体のバランスを取る役割も果たしていると考えられます。
- 重い展開が続くと読者も疲れる → ギャグで緩急をつける
- キャラ同士の関係を強調する → ふざけ合うことで親しみやすさを演出
こうした視点で見ると、ギャグの役割が単なる笑いではなく、物語の雰囲気や流れを調整する重要な要素であることが分かります。
次章では、呪術廻戦のギャグの魅力を総括し、作品全体における意義を考察します。
まとめ|呪術廻戦のギャグの魅力とは?
呪術廻戦のギャグは、一部の読者から「寒い」と感じられることがあります。
しかし、その背景にはキャラクターの個性や、物語全体のバランスを取る役割が隠されています。
呪術廻戦のギャグが持つ意味
- キャラクターの性格を際立たせる
- シリアスな展開とのコントラストを生む
- 物語全体の緩急をつける
特に五条悟や虎杖悠仁のギャグは、呪術界の厳しさと対照的な存在として、物語のアクセントになっています。
また、ギャグのセンスには昭和・平成初期の影響が見られるため、その文化的背景を知ることで楽しみ方が広がるかもしれません。
「寒い」と感じるかどうかは個人の感性によりますが、呪術廻戦のギャグにはキャラクターや物語の魅力を引き出す役割があることを理解すると、より深く作品を楽しめるでしょう。
- 呪術廻戦のギャグは、昭和・平成初期の要素が多く含まれている
- キャラクターの性格や関係性を表現するためにギャグが使われている
- 五条悟や虎杖悠仁のギャグは、物語の緩急をつける役割を持つ
- ギャグの背景を理解すると、より深く作品を楽しめる
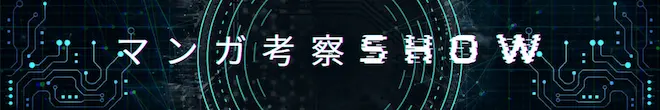
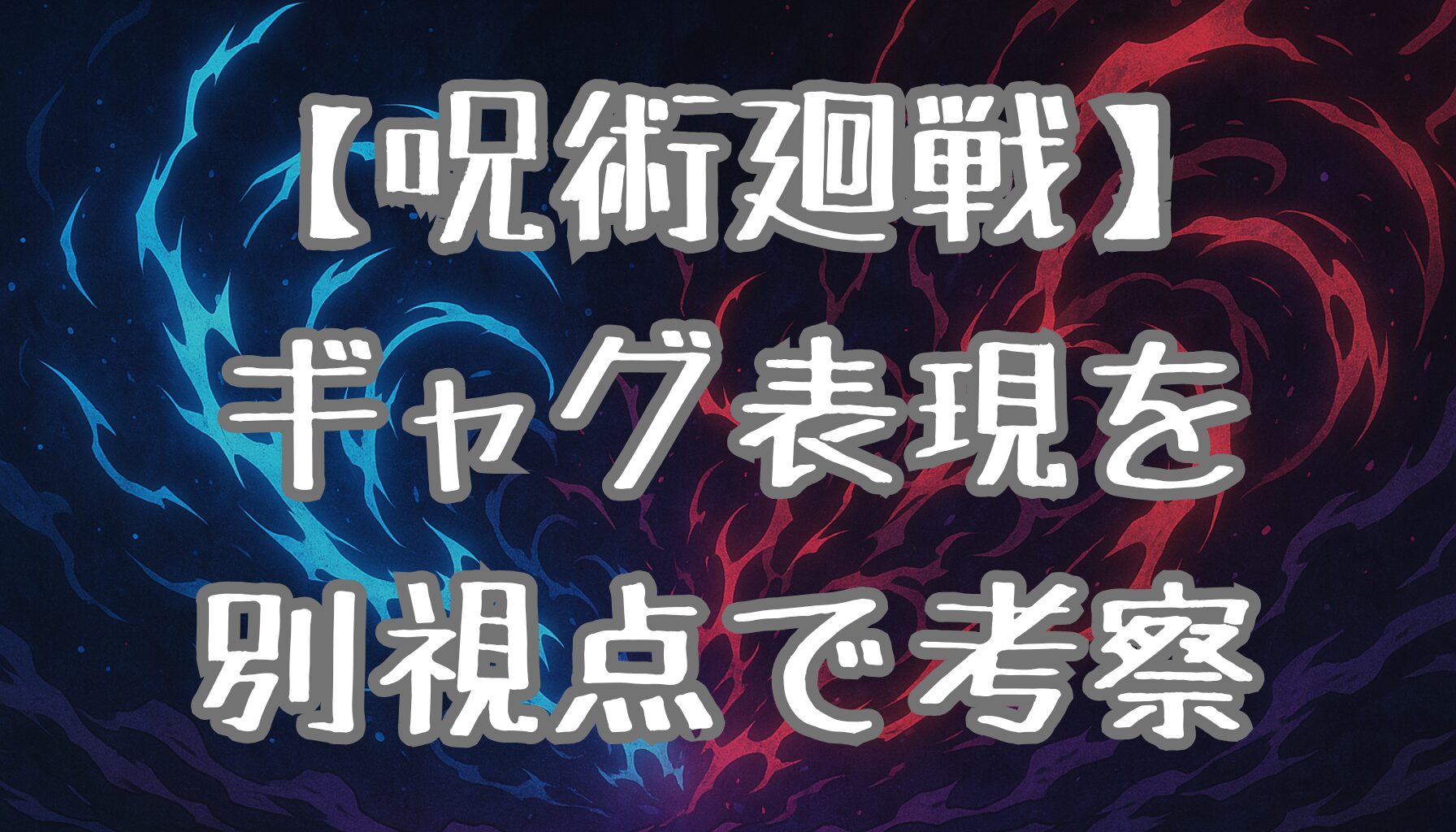

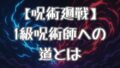
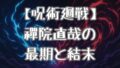
コメント